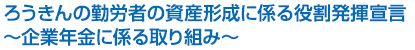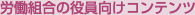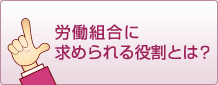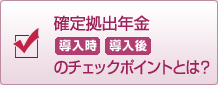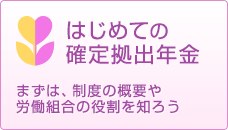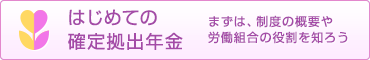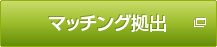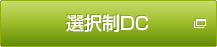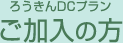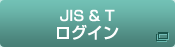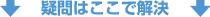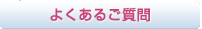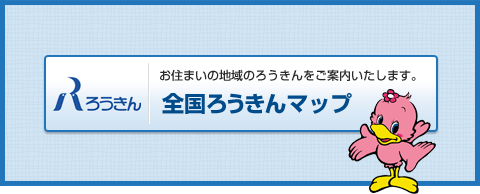ポータビリティの仕組みと自動移換の注意点
DCにはポータビリティがあり、転退職の際にその資産を移換することができます。ただし、所定の期間内にポータビリティの手続きを行わないと、資産が国民年金基金連合会に自動移換されてしまうので注意が必要です。
 ここがPOINT!
ここがPOINT!- DCとポータビリティ
転退職等があっても、継続して資産形成を行うことができます
ポータビリティとは「持ち運べること(可搬性)」を意味しています。例えば、携帯電話の番号を変えずに事業者を変更することができる仕組みを「番号ポータビリティ」といいますが、こうした仕組みは以前にはなかった便利なものです。
DCにもポータビリティがあります。DCは原則として60歳まで資産を受取ることができず、資産形成を続けていかなければなりません。そのために転退職等があっても資産を移換できる仕組みが用意されているのです。
DCは60歳までは資産を受取れないことがデメリットだといわれますが、見方を変えてみるとポータビリティがあることにより、セカンドライフのための資産形成が中断せずに続いていくと捉えることもできます。セカンドライフのための経済的準備が重要となっている現代において、資産移換の仕組みは上手に活用するべきでしょう。
- ポータビリティの仕組み
-
-
ケース
1企業型DCからiDeCoへのポータビリティもっとも多く生じるのは、企業型DCに加入していた人が、その会社を退職したことによりiDeCoに移るケースです。企業型DCではその会社を退職すると加入資格を失いますので、これまでの資産を持って、その制度の外に出て行かなければなりません(企業型DCに加入した状態で支給開始年齢を迎えた場合は、そのまま企業型DCから老齢給付金の受取りができます)。
転職した場合、転職先で企業型DCを実施していれば、転職先の企業型DCに資産を移換できます。
退職をして公務員や自営業者になった人、企業型DCのない会社に転職した人、求職活動中の人、結婚を機に専業主婦(夫)(国⺠年⾦の第3号被保険者)になった人などは、企業型DCの資産をiDeCoに移換することになります(または、通算企業年金に移換も可能です)。iDeCoでは、加入者もしくは運用指図者になることができます。
-
ケース
2iDeCoから企業型DCへのポータビリティ次のような場合、iDeCoの加入者(あるいは運用指図者)であった人は個人の申し出により、企業型DCに資産を移換することができます。(iDeCoを継続することも可能です。)
まず、自営業者や無職で、iDeCoの加入者であった人が、企業型DCを実施する会社に就職した場合です。iDeCoの資産については、就職先の企業型DCに資産を移換することが可能です。会社の担当者に「iDeCoに加入していました」と告げれば、必要な手続きを指示されます。
また、企業型DCを実施していない会社に勤めていたためiDeCoに加入していたが、その会社が企業型DCを開始した、あるいは転職した先が企業型DCを実施していた場合も、新しい企業型DCに資産を移換することが可能です。会社の担当者にその旨を告げれば、手続きを指示されます。
※就職先の会社が企業型DCではなく、厚生年金基金を実施している場合はそのままiDeCoを継続することになりますが、転職先に確定給付企業年金があり、規約において資産受け入れが可能な旨が定められている場合には、移換が可能です。
-
ケース
3他の企業年金からDCへのポータビリティ他の企業年金からDCへのポータビリティもあります。
例えば、前の会社で確定給付企業年金を実施しており、退職時に一時金を受取る権利があったとします(厚生年金基金に加入しており、プラスアルファ部分について一時金を受ける権利があった場合も同様)。この場合、一時金として受取らず、転職先の企業型DCやiDeCoに資産を移換することができます(脱退一時金相当額)。
また、企業年金連合会に脱退一時金相当額等を移換している人が、本人の申し出によりDCに資産を移換することも可能です。ただし、すでに企業年金連合会の老齢年金給付の受給権が生じている場合や、国の厚生年金の代行部分については移すことができません。
上記で触れていない制度も含めたポータビリティは以下の表のとおりです。
移 換 先 確定給付
企業年金企業型DC iDeCo 中小企業
退職金共済移
換
前確定給付
企業年金○ ○※1 ○※1 ○※3 企業型DC ○ ○ ○ ○※3 iDeCo ○ ○ ― × 中小企業
退職金共済○※2
※3○※2
※3× ○ - ※1:確定給付企業年金からDCへの移換は、本人の申出により脱退一時金相当額を移換可能。また、2022年5月の制度改正以降、終了(*)した確定給付企業年金からiDeCoへの年金資産の移換が可能となりました。
*在職中に加入していた企業年金制度が廃止され、新制度へ移行した場合など - ※2:中小企業退職金共済に加入している企業が、中小企業でなくなった場合に資産の移換が可能。
- ※3:合併などの場合に限り移換が可能。
企業年金間のポータビリティの要件、手続きは各制度により異なりますので、詳しくは各制度の担当者等に確認してください。
-
- 手続きをしないで6ヵ月経過すると自動移換される
退職後6ヵ月以内にポータビリティの手続きを行わないと、自動移換されます
退職して企業型DCの加入資格を失ったにもかかわらず、ポータビリティの手続きを行わなかった場合、原則として6カ月を経過すると国民年金基金連合会に強制的に資産の移換が行われます。これを「自動移換」といいます。
ただし、新たに確定拠出年金制度(iDeCoまたは企業型DC)に加入している場合は、その確定拠出年金制度へ移換されます。なお、他人の口座へ誤って移換してしまうことを防ぐため、新たに加入している確定拠出年金制度の基礎年金番号・性別・生年月日・カナ氏名のすべての項目の一致が確認できない場合は、国民年金基金連合会へ自動移換されてしまいます。
自動移換されると運用指図はできず、手数料だけが控除されるほか、通算加入者等期間にも算入されません。また、掛金の拠出、年金給付の請求なども行うことができませんのでご注意ください。
DCのポータビリティは自分の年金資産を守っていくための仕組みですから、手続きも原則として自分で行わなければなりません。不明な点は加入していた企業型DCの運営管理機関に問合せしましょう。
労働組合の役割
転退職時には、場合によっては会社がポータビリティについて説明をすることが前提となりますが、組合員の資産の確保のため、手続きの説明会の開催を会社に求めることや、独自に開催するなどの検討が必要です。
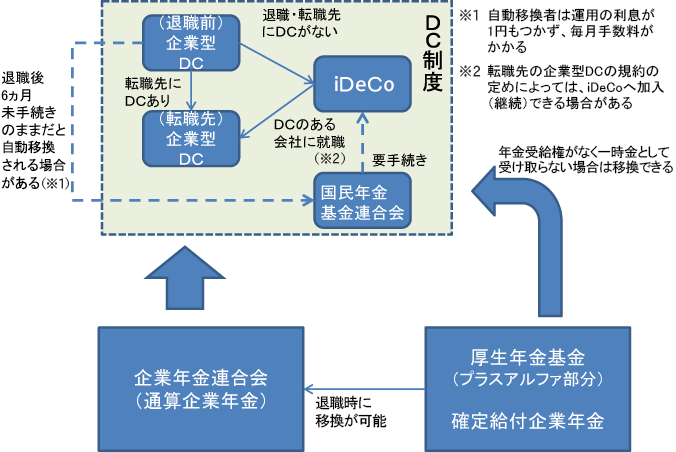
- ポータビリティの仕組みと自動移換の注意点<まとめ>
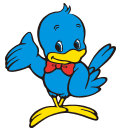
-
- 年金資産を移換することができます
- DCでは、転退職の際にその資産を移換することができ、60歳まで継続して資産形成を行うことができます。
- ポータビリティの手続きを行わないと自動移換されます
- 退職後6カ月以内に手続きを行わないと、資産が国民年金基金連合会に自動移換されてしまうので、労働組合としては、退職後のポータビリティや手続きについて説明するとよいでしょう。
- 60歳前に転退職された方(iDeCo)