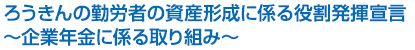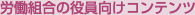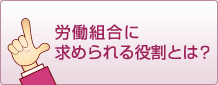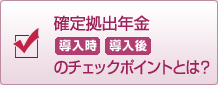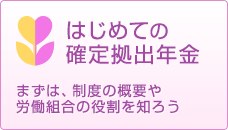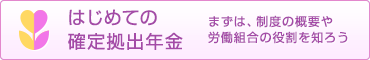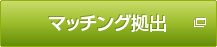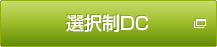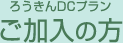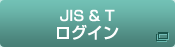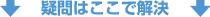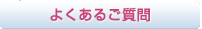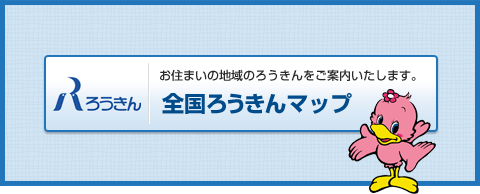DBとDCの比較表
これまでは厚生年金基金と適格退職年金が企業年金の主流でしたが、2001年(DC・DB法制定)以降、減少の一途をたどり(適格退職年金は2012年3月末で制度廃止)、現在では確定給付企業年金(DB)と確定拠出年金(企業型DC)が企業年金の主流となっています。
DBとDCは、それぞれに特徴があり、対照的な部分も多くありますが、どちらが優れているとは一概に言うことができません。検討にあたっては、それぞれの制度の長所・短所や現行制度の実態、問題点などを把握し、見直し理由や期待する効果を整理したうえで、自社に相応しい制度を判断する必要があります。
<確定給付企業年金(DB)>
従業員にとって
会社にとって
メリット
従業員にとって
- 資産運用を会社が行うため、資産管理に気を使わずにすむ
- 年金の受取り見込額がわかりやすいため、老後の生活設計が立てやすい(デメリットも参照)
- 年金受取りを前提に設計されているため、老後の安定的な収入源となる
会社にとって
- 給付額が約束された企業年金制度を有していることで人材獲得、従業員のロイヤリティ向上につながる
- 自己都合退職者や懲戒解雇者に対して減額支給が可能
- 掛金拠出に税制優遇措置が講じられているため、退職一時金より効率的に資金準備ができる
デメリット
従業員にとって
- 勤続年数にかかわらず給付減額の可能性がある(受給者も同様)
- 積立不足の償却負担が重い場合、業績が圧迫されて給料などに悪影響を及ぼすことがある
- 今自分が獲得している受給権がわかりにくい
会社にとって
- 退職給付会計の対象となるため、従業員に支給される退職給付のうち認識時点までに発生しているものを退職給付債務として認識しなくてはならない
- 資産運用の責任を負う
- 積立不足が生じる可能性があるため、将来の掛金負担が不確定である
<確定拠出年金(企業型DC)>
従業員にとって
会社にとって
メリット
従業員にとって
- 今いくら残高があるか確認できる
- 受給権が確立しており、勤続3年以上であればどのような理由でも減額されない
- 自身のDC資産のみ管理・運用すればよく、現役世代や退職者等(受給権者)の資産の運用リスクを負うことはない
会社にとって
- 積立不足が生じないため、将来の掛金負担が安定的になる
- 退職給付会計の対象外となるため、退職給付債務が生じない
- 他社の企業型DCから資産の受け入れが可能となるため、有力な人材の確保につながる
- 従業員に退職給付の「見える化」が期待できる
デメリット
従業員にとって
- 資産運用を自ら行わなければならない(自己責任)
- 価格変動が生じるため、受取額が見込みでしか計算できない
- 原則として60歳以降でないと受給できないため、中途退職時の生活費や独立資金としては用いることができない
会社にとって
- DCでも制度の運営は会社が担うため、DB同様、事務コストが発生する
- 継続的な投資教育を実施する責務がある
- 勤続3年以上の自己都合退職者や懲戒解雇者について減額支給ができない