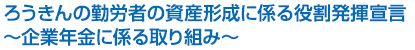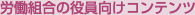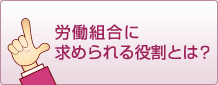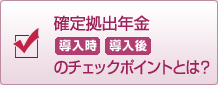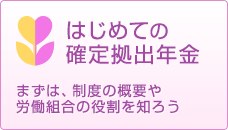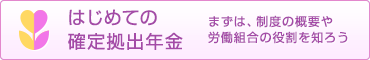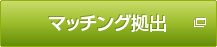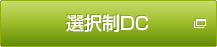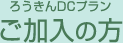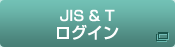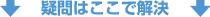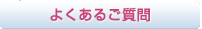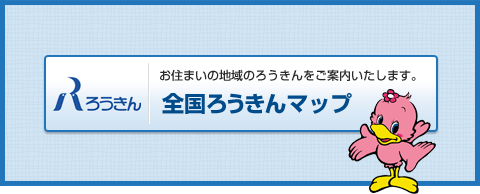加入について
確定拠出年金の加入対象者を定める際は、特定の者に対して不当な差別とならないよう合理的かつ客観的な基準が必要になります。法令で定められた4つの加入資格ルールを解説します。
- 企業型DCを始めるにあたり
厚生年金の被保険者から加入対象者を定めることができます
企業型DCを採用するにあたっては、まず誰がDCの加入対象者となるかを定めなくてはなりません。
加入者となりえるのは厚生年金の被保険者で、規約に加入対象者を定めない場合には、会社に勤務する厚生年金被保険者の全員が企業型DCの加入者となりますが、多くの企業で加入者となりえる資格を規約に定めています。ただし、加入資格については自由に定めていいわけではありません。例えば、経営者の一存で加入の権利が与えられる(あるいは与えられない)ようなことはあってはならないわけで、不当に差別的な取扱いとならないよう、合理的かつ客観的基準が定められています。
なお、非正規従業員であっても厚生年金の被保険者であれば企業型DCの加入対象となりえますが、労働条件が正規従業員と著しく異なる場合は、代替制度を設けずに加入対象外とすることも認められています。
- 法令で定められた加入資格のルール
4つの加入資格ルールが法令で定められています
-
ルール
1一定の職種一定の職種に属する従業員のみ加入対象者とすることができます。
なお、職種とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協約や就業規則などにおいて、労働条件が他の職の従業員とは別に規定されていなければなりません。 -
ルール
2一定の勤続期間一定年数働いた従業員に退職金の受給資格を与えることが日本の労働慣行として見受けられます。3年あるいは5年や10年といった節目を設定することが多いようです。
DC制度についても一定年数の勤続期間(以上もしくは未満)を加入要件とすることが可能です。この場合「勤続3年を経過した者を加入者とする」のように加入の条件を明示します。
ただし、それ以前の勤続期間については何かしらの代替給付が必要とされます。入社3年を加入要件としたならば、入社時点から3年間はDC掛金と同等額を何らかの代替給付しなければならないのです。前払いの退職金制度として給料や一時金に同等の給付を加算することが一般的です。 -
ルール
3一定の年齢「50歳以上」を企業型DCの加入対象外とし、旧制度での給付を保証するような取扱いが認められています。
一定年齢以上の従業員は、中長期的な資産運用を行う期間がないので、短期的な市場の下落が生じると、DCの資産価値が大きく下落したまま退職・給付を迎えるリスクがあるからです。なお、50歳未満に設定することはできません。 -
ルール
4希望者(加入の選択)加入そのものを選択できるようにすることも可能です。
DCは、60歳前の中途退職者でも、原則一時金として受取ることができないので、「加入する」「加入しない」を任意で選ばせる取扱いが認められています。
ただし、「加入しない」とした人について、DC制度に加入した人と同程度の代替給付をしなければならず、多くの企業は、代替給付の措置として、前払い退職金制度を設けています。
加入資格ルールは自由に組合せができます
これらの4つの条件は組合せることもできますし、採用しないこともできます。
加入資格ルールについては労使間で話し合いながら、会社の人事制度との整合性も検討しつつ決定していきます。-
- 加入について <まとめ>
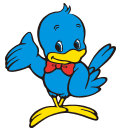
-
- 企業型DCの加入対象者は、厚生年金の被保険者
- 企業型DCの加入者となりえるのは、厚生年金の被保険者です。規約に加入対象者を定めない場合には、厚生年金被保険者の全員が企業型DCの加入者となります。
- 4つの加入資格ルールを自由に組合せることができる
- 一定の職種、一定の勤続期間、一定の年齢、希望者(加入の選択)の加入資格ルールを自由に組合せて、加入対象者を定めることができます。
- 企業型DCの加入者とならない従業員への代替措置が必要
- 厚生年金の被保険者で、企業型DCの加入者とならない従業員には、旧制度での給付を保証したり、前払い退職金を給付するなどの代替措置が必要です。
ただし、非正規従業員などで労働条件が正規従業員と著しく異なる場合は、代替制度を設けずに加入対象外とすることも認められています。