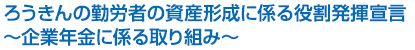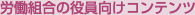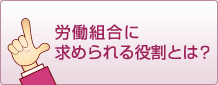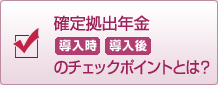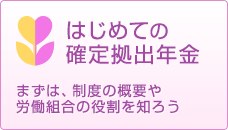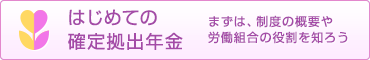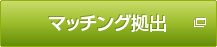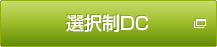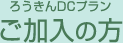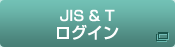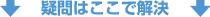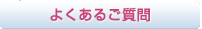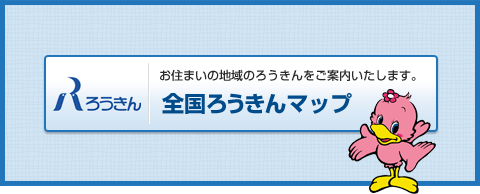導入までの流れ
確定拠出年金(企業型DC)を導入する際に労使合意は必須です。会社側とともに、加入者のための制度設計を行うことが労働組合の役割です。
- 確定拠出年金の導入には労使合意が必要
労働組合もしくは労働者の代表の同意が必要です
わが国の企業年金制度である厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金はいずれもその開始にあたって(あるいは制度の変更に際して)労使合意が求められます。
具体的には設立にあたり、労働組合(厚生年金被保険者の過半数で組織すること)の同意、そのような労働組合がない場合には、厚生年金被保険者の過半数を代表する労働者代表の同意が必要になります。かつて適格退職年金制度の設立に際して労使合意が求められなかったことや、退職金規程の改定に必ずしも労使合意を要しないことを考えると、確定拠出年金の開始や見直しに際して、労働組合の同意を必要とすることは労働者にとって大きな前進です。
労働組合には、DC制度の導入とその運営について大きな責任があります。制度改定の提案を受け身として捉えるのではなく、主体的に関わっていくべき問題と考えなければなりません。
- DC導入について労働組合はどこまで関わるか
制度設計の協議にも参画する必要があります
DC導入にあたっては、根本的な「DC制度導入の同意」だけではなく、規約策定の内容についても同意をしていく必要があり、労使間での話し合いの中で制度設計そのものにも意見を述べる機会があります。
退職給付制度の変更は不利益変更の可能性と直結していますから、制度の変更前後において旧制度と新制度で受給権がどのように変更されるのかも厳しくチェックしなければなりません。仮に給付が引下げられるとなれば、どのような理由によりどの程度の引下げが行われるのか、あるいは代替的な措置や経過措置は設けられるのか、労働組合はチェックする必要があります。
また、制度の円滑な導入に向けて、運営管理機関の選定コンペや運用商品の選定、会社が行う導入時教育の内容にも意見を述べ、支援することも必要です。加入者が自己責任で資産運用を行えるよう、会社とは別途相談室を設けたり、セミナーを開催する労働組合もあります。
- 労使合意すべき事項
想定利回りの設定が交渉の肝
DC制度の規約についてはすでに解説したようなポイントを確認しながら進めていきます。
- 加入者資格の設定
- 掛金の設定(および想定利回り)
- 給付の設定
- マッチング拠出(加入者掛金)の有無
- 運用商品の選択肢
- 投資教育の内容
- 短期離職者(勤続3年未満)の掛金の事業主返還ルール
(いわゆるべスティングルール) - 費用負担を求められる場合、その条件
- 他制度から資産を移換する場合、その条件
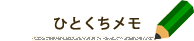
- 特に、想定利回りの設定は掛金の設定にも直結し、加入者の将来の受給額に大きく影響するので、交渉の肝であるといえます。
等について、規約の内容を一つひとつ確認しながら、加入者に不利益が生じていないか交渉を行っていきます。
DC制度は一度スタートすれば、これから数十年以上にわたって労使が適切な運営を考えていかなければならない制度です。将来「やっぱりDB制度がよかったので戻そう」というようなことは簡単にできることではありません。
不明な点については、資料提供や納得のいく説明を求めるなどして、懸案を将来に残さないようにすることが必要です。
- 制度検討前からの関わり方
会社側の制度検討の勉強会にも積極的に参加を
DCの導入に関する会社から労働組合への提案は、DC導入ありきの提案であったり、DCの制度設計が固まっている段階で初めて打診されることも想定されます。労使協議のタイミングに関してのルールはないので、会社側は何カ月も前から、金融機関やコンサルティングの助言を得ながら勉強会や検討プロセスを重ねた後に、労働組合へ提案をしてくることもあります。
労働組合側の準備がない中でいきなりDC導入の是非を求められても、加入者の利益を守るための労使交渉はスムーズにいきません。
むしろ検討段階の早期に会社側と接触をし、制度検討の勉強会や検討プロセスの初期段階に関わっていくことが、その後の労使協議にプラスに働きます。もし退職給付制度の改定に関する勉強会等を会社が行っているようでしたら(受託金融機関やコンサル会社を招くことが多い)、近い将来制度改定の提案が行われる可能性があります。
この段階から労働組合も同席し、労使が共通の知識を持ち、建設的な議論を行えるようにしておくことが有効です。DC業務を委託する運営管理機関の選定についても、会社は、3社以上を招いてコンペを行うこともありますので(DC規約の承認審査の際に比較検討を行ったかどうかヒアリングされるため)、こうした機会には労働組合も同席し、加入者の代表として投票に参加することが望ましいでしょう。
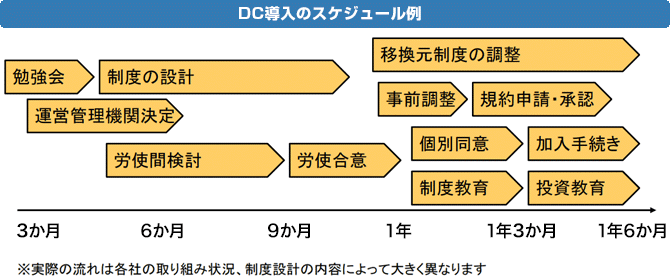
- 導入までの流れ<まとめ>
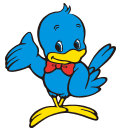
-
- 早い段階で労使間の認識の共有をすることが重要
- 会社側から導入の提案を受けてから動いたのでは遅く、建設的な労使交渉を行うことが難しくなります。日頃から、あるいはできるだけ早い段階で、会社と認識を合わせておきましょう。
- 労使交渉では加入者の利益を第一に
- 運営管理機関や運用商品の選定は、資本関係があるから等の理由ではなく、法令上、加入者の利益を第一にしなければなりません。労働組合の視点からも充分チェックしましょう。
- 導入後の支援も必要
- 加入者が自己責任で資産運用を行えるよう、事業主による継続的な投資教育の実施等、しっかりとしたサポートが行われるよう、導入までに労使で確認しておくとよいでしょう。